祓戸大神(はらえどのおおかみ)のこと
- 瀬織津比売神(せおりつひめ) -- もろもろの禍事・罪・穢れを川から海へ流す
- 速開都比売神(はやあきつひめ) -- 河口や海の底で待ち構えていてもろもろの禍事・罪・穢れを飲み込む
- 気吹戸主神(いぶきどぬし) -- 速開都比売神がもろもろの禍事・罪・穢れを飲み込んだのを確認して根の国・底の国に息吹を放つ
- 速佐須良比売神(はやさすらひめ) -- 根の国・底の国に持ち込まれたもろもろの禍事・罪・穢れをさすらって失う
**************************************************
明治政府は「神仏分離」政策を推し進め、神社から仏教的な要素を排除しました。これにより、神仏が習合していた場所では祭神の変更や神仏混淆の否定が起こりました。また、特定の神官を退けたり、祭神を「正しい」とされるものに改めたりする動きもあった
**************************************************
梓川水系のこと
日本三代実録」の貞観9年(867)の条には、正六位梓水神とありますが、この梓水神こそ乗鞍岳で、古くはその逢拝所が大野川の宮の原にありました。ここに乗鞍岳の権現池そっくりな大池があり、人々はこの大池を神の池御池とあがめていました。古くから、この池の水をもらって苗代にまくと、よく稲ができるといい、日照りの時にもらってまくと雨が降ると伝えられ、霊験あらたかな池として知られています。
****************************************************
須々岐水神社(すすきがわじんじゃ)
「日本後紀」延暦18年(799年)12月甲戌条に、高句麗から渡来した信濃国人卦婁真老(外従六位下)は「須々岐」の姓を与えられたとある。
- 867年(貞観9年)に、安曇大野川の梓水神社とともに、正六位上から従五位下に昇叙されたと、『日本三代実録』に記録が残る。
- 1458年(長禄2年)の墨書銘をもつ木造の狛犬が残る[4]。
- 『信府統記』の「松本領諸社記」には、「薄宮大明神」として「山奥の大明神平に降りた神が、笹の葉に乗って薄川をくだり薄畑に着き、現在の社地に移った」との伝承が記録されている。
*************************************************************
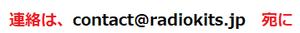

コメント